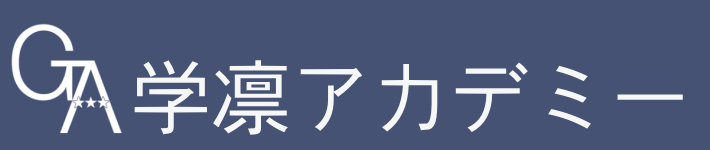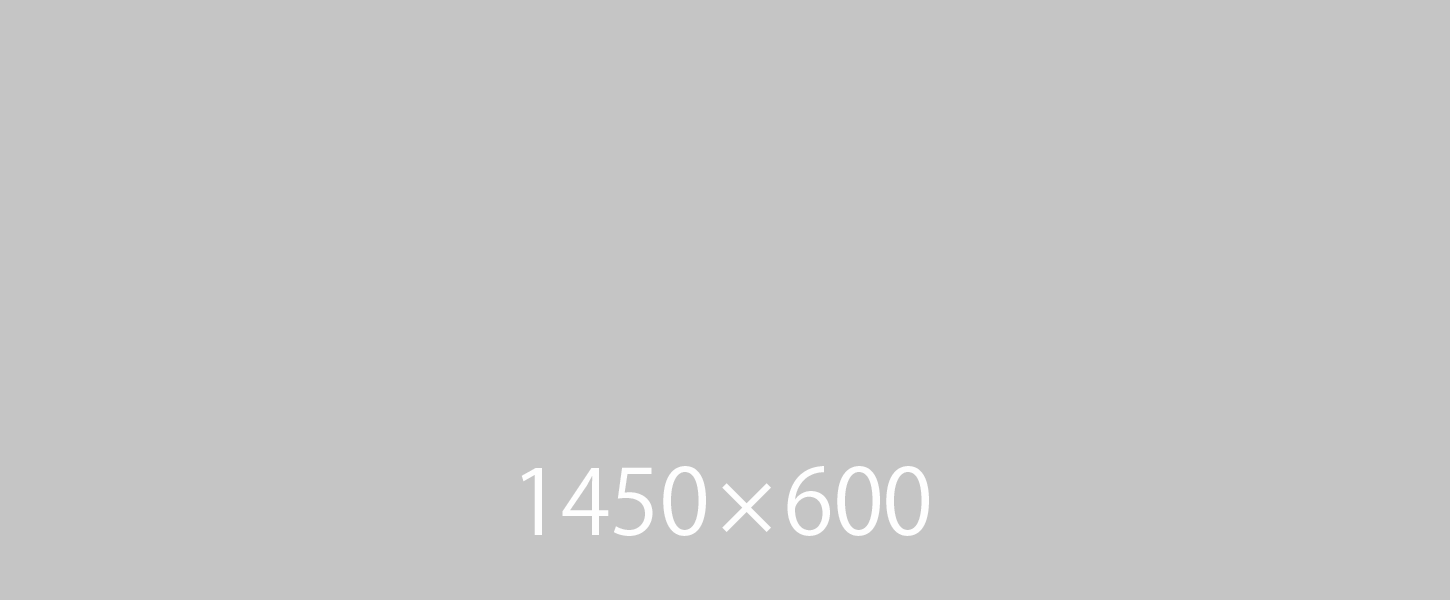【富山 介護教育】定年後に介護教育を選んだ理由 その2
校長せんせいのこぼれ話 第2号
前回は現役時代での介護との関係をお話ししました。
定年後に短大へ入学し、そこで介護の勉強に取組みました。その時は、卒業したら障害施設か高齢者施設で介護の仕事に就こうと漠然と考えていました。今回はその後どのようにして介護教育の分野へと進んだのかをお話させていただきます。
定年後に短大へ入学し、そこで介護の勉強に取組みました。その時は、卒業したら障害施設か高齢者施設で介護の仕事に就こうと漠然と考えていました。今回はその後どのようにして介護教育の分野へと進んだのかをお話させていただきます。
介護教育へのかかわり(終章)
今でこそ、介護事業に外国の方が就労されるのは珍しくない事ですが、10年前は、外国人に介護現場に就労してもらい、初任者研修を実施したいと考えている施設は本当に珍しかったです。そのような施設へ勤めているとき、介護の仕事のかたわらで初任者研修を企画してほしいといわれました、私が仕事として、初めて介護教育にかかわった瞬間でした。
その後、別の施設からも実務者研修を企画してほしいとお話を受け、本格的に介護教育にかかわることになったわけです。
その後、別の施設からも実務者研修を企画してほしいとお話を受け、本格的に介護教育にかかわることになったわけです。
県への申請は県庁のご担当者からお教えいただき、何とか進めることができました。
しかし、実際に働きながら勉強を進めていくような研修は大変ハードです。本当に受講者のためになるような研修は何か、というところから考えました。
しかし、実際に働きながら勉強を進めていくような研修は大変ハードです。本当に受講者のためになるような研修は何か、というところから考えました。
しかし、私には経験がないので、どこから手を付けていいのかもわかりません。
当時から初任者研修や実務者研修を実施している学校は多くありました。そこで私は経験を積むためにいろいろな学校へ見学をお願いして廻りました。予想どおり、全てお断わりされました。
当時から初任者研修や実務者研修を実施している学校は多くありました。そこで私は経験を積むためにいろいろな学校へ見学をお願いして廻りました。予想どおり、全てお断わりされました。
そこで、現役時代大変お世話になったヘルパー2級研修(現初任者研修)の学校に、「学校を開設したいんです。県庁にも申請しました。ただ、どのような研修をすればよいのかよくわからないので教えてください。」と正直にお願いしました。
そこの校長先生は、「話はわかった。しかし、私は富山には行ったこともないので、どんな教室を開いたら良いのか指導もできない。」と、わざわざ富山まで来てくださいました。
校長先生が来て下さらなければ、間違いなく今の私はありません。本当に感謝しています。現役時代、私は「現場主義」を徹底されていましたが、介護教育においても「現場主義」があることをこの校長先生から学びました。
現在は多くの出版社が自社テキストにあったeラーニングシステムを安価で提供しています。しかし、当時は専門学校等は全国共通のeラーニングシステムを持っていたのですが、一般学校では独自のeラーニングシステムを開発・運用しており、受講料が高額になる要因の1つになっていたのです。
eラーニングシステムを準備できない学校は、手書きの問題で運営していました。初任者研修ではいまだに手書き問題で運営しているところが多く見られます。受講者もスマホやPCが苦手という方が多く、手書きの方が良いと言っている学校もありますが、私は反対です。
これだけ介護職の不足が深刻化している現状では、少しでも利用者と介護職の関わりを多くする必要があります。そのためには、利用者との関わり以外の介護職の仕事効率化を進める以外にはないと考えています。仕事効率化にはICTの導入は不可欠です。実はeラーニングに必要なICTの知識は簡単なものです。他の資格取得の現場では広く使われています。なので初任者研修でも、eラーニングが普及することを願っております。
私がかかわった学校では、このeラーニングシステムを構築することができなかったです。そのため、eラーニングシステムを運用している様々な学校と契約を締結して、演習だけを自校で実施していました。そのおかげで、いろいろなeラーニングシステムや問題・テキストを使用することになりました。その経験は、今となってはとても重要なノウハウの蓄積になりました。
問題を解こうと思っても、指定テキストに解答がないシステムもありました。コメントや様々な案内を送れるという、28,000円/1人もする高度なシステムもありました。事務局には便利でも、受講者のためにならないと思って、すぐに乗り換えました。
テキストもこの科目は良いが、別の科目は別のテキストが良いというものもあります。出版社のeラーニングシステムでは、最適なテキストを選ぶことはできないのです。
そのような苦労の中で、いつか独自のテキストで独自のeラーニングシステムを持ちたいと思ってきました。当校では現在、90パーセントはかなえることができました。
残る課題がeラーニングシステムの多言語化です。この課題については、「そもそも、eラーニングシステムを多言語化して良いのか?」厚労省、県への確認が取れていません。介護福祉士国家試験を受験する外国人に問題のフリガナ付き、時間延長だけで、済ませている現状の中で、難しいとは思いますが、今後、取組みたい課題です。