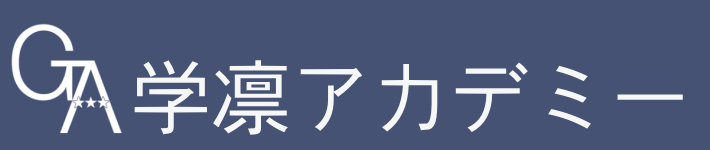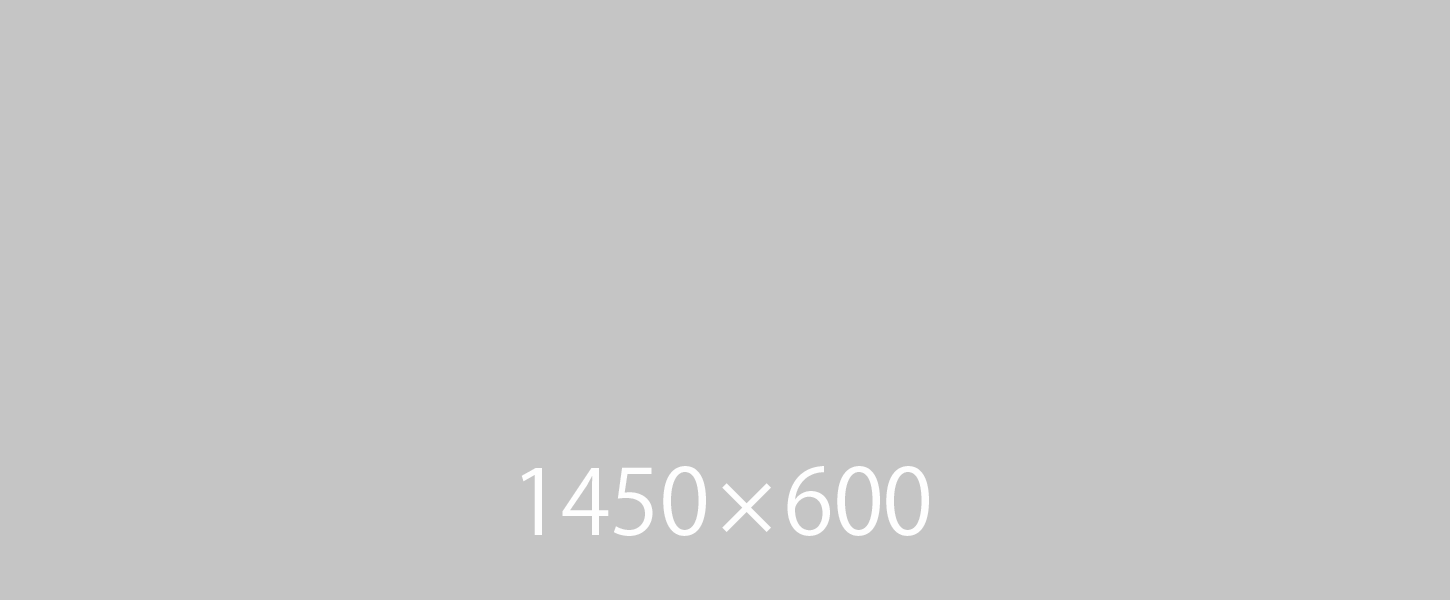【富山 介護教育】定年後に介護教育を選んだ理由
校長せんせいのこぼれ話 第1号
介護教育にかかわって10年、まだまだ未熟です。異業種から入ったからこそわかること、どうしても理解できないこと、こういう勉強をしたかったということなどをお話しすることも、介護教育に何かお役に立てることもあるかと思い、連載することになりました。月に数回、掲載しようと思っています。
介護教育へのかかわり(前章)
私は、メーカー人事一筋で、10数年前に定年退職を迎えました。
話は私の現役時代にさかのぼります。今から20年前、まだ国のサービスとして年金情報もありません。当時、50代の従業員は定年後、どんな生活が待ち受けているのかもわからない状態で、不安だったのです。
私の働いていた会社では、国から従業員の年金データ(はじめは紙データの提供)を入手して、従業員の老後不安を払拭すべく、セミナーを開設していたのです。
「熟年設計セミナー」という研修で土曜日1日を夫婦、参加するセミナーでした。
当時、私は「熟年設計セミナー」テキストの作成や、セミナー講師養成に従事していました。
「熟年設計セミナー」は50代受講生夫婦が会社の用意した年金データをもとに退職金や年金を計算して、その資金を元に、自分達の老後における経済設計、趣味等のゆとり計画を1日がかりで作っていくものです。例えば、持ち家ローンが定年時には完済できるであろうと、一安心していた夫婦は、リフォーム費用がかなりかかることで、今までの老後資金を見直す機会にもなりました。
私の介護のかかわりもこの時からだったのです。
「熟年設計セミナー」で立てた経済設計、ゆとり計画も、ひとたび、ご両親、自分、配偶者が介護を受けるようになったら一から見直さなければいけません。当時は民間介護保険も種類が少なく、月額2万円もするようなものしかなく、一般的ではありませんでした。私は福祉分野を担当した頃(今から30年前)に民間介護保険を契約していました。民間介護保険は介護リスクをカバーできるものとはいえるものではなかったのです。
セミナーで何か他に介護リスクについて、お話できたらと思っていたのですが、介護に関する知識もなく、かなわなかったのです。そこで、会社が休みの時にヘルパー2級(現初任者研修)を受講したのです。それが介護との最初のかかわりだったのです。しかし、残念なことに、ヘルパー2級の知識だけでは、テキストに介護リスクについて掲載することはできませんでした。
介護の次のかかわりは、それから10年後、定年退職後に訪れました。
定年後、再就職のためにハローワークに行くと、社会人入学対象の福祉系短期大学を紹介されました。メーカー人事をしていた者がヘルパー2級を持っているのを不思議に思ったハローワーク職員が、私の話を聞いてくれ、紹介してくれたのです。まさに、「資格が身を助く」になったのです。
短大の2年間、40歳も歳の離れた若者に混じって、毎日、福祉の勉強をしました。
会社員が退職をすると、定年後の一時期、会社生活のストレスから放たれ「定年ハネムーン」という現象が起きると言われていますが、私にとってはあれだけわからなかった介護について、毎日、理解が深まり、「福祉ハネムーン」だったのです。
会社員が退職をすると、定年後の一時期、会社生活のストレスから放たれ「定年ハネムーン」という現象が起きると言われていますが、私にとってはあれだけわからなかった介護について、毎日、理解が深まり、「福祉ハネムーン」だったのです。
また、今からすると、介護を目指す若者の本音を聞くことができたまたとない時期だったとも言えます。
こぼれ話と言いながら、長くなってきたので、介護教育へのかかわりについては2号にお話しさせていただきます。